季節を編む暮らし ― 家族の手しごと帖(保存食篇)
2025/9/3
【畑とキッチンがつなぐ、家庭の食文化】
鈴虫の奏でる季節となりました。北海道移住より19年の歳月が流れて迎える2025晩夏~初秋。
・
この時期になると、家庭菜園では野菜やハーブたちが「もういいよ」と言わんばかりに一斉に実りはじめます。本州と比べて、四季のメリハリがはっきりしている北海道では、うかうかしていられません。収穫のタイミングを逃せば、霜、そして雪。のんびりしていたら、一瞬で冬に飲み込まれてしまいます。
・
だからこそ、この時期は台所も畑も少しピリッとした緊張感に包まれます。

でもね、その忙しさの中にこそ、小さなよろこびが詰まっているのです。
・
トマトが割れないうちに収穫して、ナスの色があせないうちに調理して。時には手間のかかる作業もありますが、一度瓶に詰めてしまえば、冬の間は「パカッ」と開けるだけで、すぐに食卓へ。あの時の手間ひまが、冬の食卓に「ありがたいねえ」と感謝となって帰ってくる。
・
それって、ちょっとした魔法じゃないですか?

保存食って、ただの作り置きではないんです。
・
そこには、昔から続く「暮らしの知恵としてのDNA」と「家族の文化」がしっかり根を張っています。
・
冷蔵庫も冷凍庫もない時代。長い冬を生き抜くために、私たちの祖先は工夫を重ね、手を動かしながら命をつないできました。それが今も、私たちのどこかに息づいている気がします。
・
もしかしたら、保存食を作るたびに、私たちはその「記憶のバトン」を受け取っているのかもしれません。
・
私のふるさと、ルーマニアも同じです。
この季節になると、早朝4時から母とおばあちゃんがキッチンで大忙し。コンロの火がついて、ナスやパプリカを真っ黒になるまで焼き続ける。その熱気にキッチンは別世界みたいになっていて、うっかり入ろうものなら、「見てわかるでしょ!? 今忙しいの、あとで食事持ってくから!」と追い出されるのがオチでした(笑)。
・
それでも私は、あの風景を見るのが大好きでした。
・
ナスの皮を剥いて、種とワタを取り出して、木べらでトントンとペーストにしていく母とおばあちゃん。瓶に詰めて、煮沸して、食品庫に並べると、ずらっと並ぶ瓶が本当に美しくて。あれは、ワタシの心の中にある「家庭の祭典」だったような気がします。

今は文明の力で冷凍もできるし、バーベキューコンロも使える。けれど、あの頃の手仕事の記憶が、毎年この季節になると、ふっと蘇ってくるんです。
・
そして、思うのです。「あぁ、ワタシたちの暮らしは、こうして季節とともに巡っていくのだなぁ」と。
・
春にタネをまき、夏は立派に育つように観察と最低限のお世話を施して、秋に収穫し、冬に備える。畑からキッチンへ、そして瓶の中へ。その循環が、暮らしのなかに静かに息づいています。
・
子どもだったワタシが母になり、祖母になり、また次の世代に手渡していく。それはたった一本の瓶詰めに見えて、実は「生きるためのDNA文化」そのものなのかもしれません。

以下は、家族や教室の生徒さんにも大人気を博してきたアイバル(≒ザックスカ)。上記のようにナスとパプリカを真っ黒になるまで燻し焼きしてから、皮を剥き、そして種とワタを取りだす。その後は、大鍋でさらに水分を飛ばしながら煮詰めていくと、アイバル(≒ザックスカ)になる。
今は便利な時代。いつでも、どこでも、何でも買えます。だけど、だからこそ「手をかけること」「保存してみること」の大切さが、じわじわと見直されているのではないでしょうか。
・
秋のひととき。ふと思い立って、ひと瓶でもいい。何かを保存してみたくなったら、それはきっと、あなたの中にある"食の記憶"が目を覚ましたサインです。
会員登録がまだお済でない方は、コチラから登録ください。

●トマトのコンフィ(サンマルツァーノなどの調理用トマト)
●大玉トマトの冷凍保存術
●冷凍パプリカ


●東欧流の炭焼きパプリカ&ナス
●東欧流・酢とうがらし
●自家製マスタード
●夏やさいのマリネ
●東欧伝統の発酵ビーツ、クヴァス(冷凍)
●セロリとパプリカのみじん切り☞そのままジップロックで冷凍(冬はスープのなかにドボンと入れるだけ)

アディナのオーガニックキッチン~ダイナミックステラ~
Facebookページも「いいね!」してください

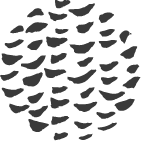 Diary
Diary